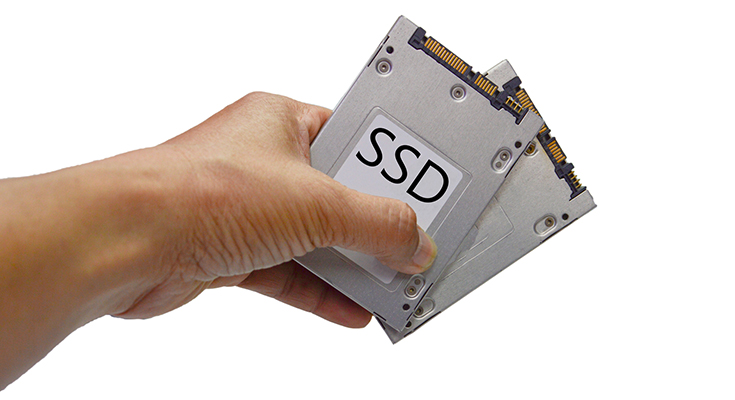HDD/SSDの規格にはどんなものがある?商品選びに役立つ規格の違い

HDD/SSDには多くの種類があります。中でも、選ぶ際に気を付けたいのが、各ストレージの規格です。性能などを左右する反面、容量とは異なり数字で比較ができないため、わかりにくいと感じている方もいらっしゃるかもしれません。ここでは、HDD/SSDを選ぶ際に役立つ、規格の違いについてご紹介します。
※この記事は2024/7/30に再編集しました。
目次
HDDの規格

HDD(ハードディスクドライブ)は、プラッターと呼ばれる回転する円盤に、磁気ヘッドを近づけることでデータを読み書きするストレージです。主な接続規格(インターフェース)としては、SATAとIDEの2種類が挙げられます。
SATA
SATA(シリアルATA/サタ)は、現在主流となっているHDDの接続規格です。SATA 1、SATA 2、SATA 3の3世代があり、最新のSATA 3が最も転送速度に優れています。世代ごとの最大転送速度(理論値)は、以下のとおりです。
aaa
- SATA 1:150MB/s
- SATA 2:300Mb/s
- SATA 3:600MB/s
SATAは、1本のケーブルで連続してデータ転送を行う「シリアル方式」を採用しているのが特長です。IDE規格のHDDよりも、データ転送速度は高速化しています。
また、各世代で互換性を備えているため、SATA 2対応の機器にSATA 3対応のHDDを接続することも可能です。ただし、データ転送速度は下の世代(SATA 2)の上限に制限されます。SATA規格のHDD本体のサイズは、2.5インチと3.5インチの2種類です。
IDE
IDE(Integrated Drive Electronics)は、SATAが普及するまで広く使われていた接続規格です。ATAやパラレルATA(PATA)などと呼ばれることもあります。IDEは、複数の線を使い並行(パラレル)してデータ転送を行うため、ケーブルが幅広いのが特長です。コネクターには多数のピンが設置されています。
SATAとIDEには互換性がなく、SATA対応のパソコンにIDE規格のHDDを取り付けることはできません。IDE規格のHDDは生産が終了しているため、基本的に見かけることはまれです。
一般ユーザーが目にすることは少ないものの、SATAやIDE以外にも、企業向けのサーバーで使われることが多いSAS(Serial Attached SCSI)といった規格があります。
SSDの規格
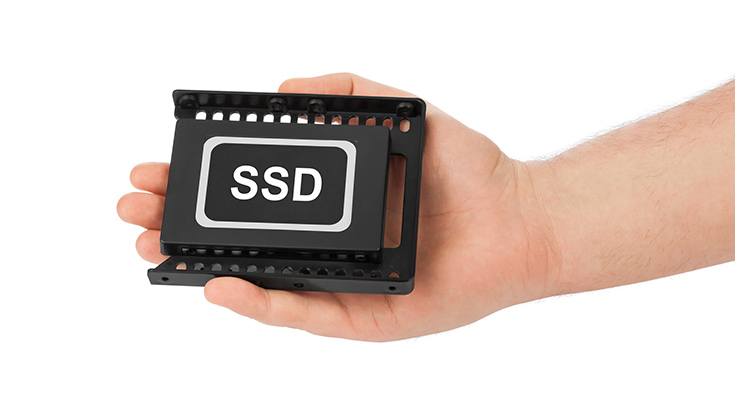
SSDは、内蔵のメモリーに電気的にデータを読み書きするストレージです。HDDとは異なり物理的に駆動する部品がないので、読み書きが高速、衝撃に強い、動作音が静かといったメリットを備えています。
近年使われることが増えているSSDですが、接続規格や形状(フォームファクタ)の種類が多く、違いがわからないという方もいらっしゃるでしょう。主なSSDの形状と採用している接続規格は、以下のとおりです。
2.5インチ
2.5インチのHDDとサイズが同じであるため、ノートパソコンやデスクトップパソコンをはじめ、幅広く使われているSSDです。一般的なHDDと同様に、接続規格にはSATA 3が採用されています。
HDDと互換性を持つため、古いHDDを2.5インチSSDに換装(交換)することも可能です。マウンタを活用すれば、パソコンの3.5インチベイにも搭載できます。2.5インチSSDの特長や選び方などは、以下の記事も併せてご確認ください。
mSATA
SATAを小型化したmSATA(Mini SATA)と呼ばれる接続規格を採用したSSDです。基板がむき出しになった形状で、パソコンのマザーボードにあるスロットに直接接続して使います。データ転送速度は、SATA 3と同様に600Mb/sです。
コンパクトなサイズが特長で、ノートパソコンの小型化にも貢献してきた規格ですが、近年はあまり使われていません。mSATA SSDの概要は、以下の記事も併せてご確認ください。
M.2
mSATAの後継規格として誕生したのがM.2 SSDです。基板がむき出しになった形状で、マザーボードのスロットに直接接続して使用します。「2242」や「2280」など、基板のサイズによって複数の種類に分けられます。
接続規格はSATA 3に加えて、さらに高速なデータ転送を行える「PCIe(PCIExpress)」に対応しているのも特長です。PCIe接続のM.2 SSDは、SSD用に最適化された「NVMe」という通信規格を使用しています。
また、本体のサイズや接続規格に加えて、端子形状も「M key」「B key」「B&M key」の3種類に分かれているため、購入する際は注意しましょう。パソコンのスロット形状がM.2 SSDの端子形状と異なる場合、機器に接続できません。M.2 SSDの詳細は、以下の記事をご確認ください。
フラッシュメモリーの規格
一般的なSSDは、NAND型フラッシュメモリー内の「セル」と呼ばれる部分にデータを保存しています。セルに保存できるデータ容量から、SLC(シングルレベルセル)、MLC(マルチレベルセル)、TLC(トリプルレベルセル)、QLC(クアッドレベルセル)の4種類に大きく分けることが可能です。
1セルに対して保存できるデータが増えるほど、低価格かつ大容量になるものの、耐久性は下がっていきます。SSDが採用しているフラッシュメモリーの概要は、以下の記事も併せてご確認ください。
外付けHDD/SSDで使われる接続規格

HDD/SSDには、パソコン本体に内蔵するモデル以外にも、パソコンやスマートフォンなどの機器に外付けして使えるモデルもあります。それらの外付けHDD/SSDの接続に使われる接続規格は、USB-AやUSB-Type-C(TM)が主流です。
USBは世代によってデータ転送速度が異なるため、購入前に確認しておきましょう。例えば、USB 5Gbps(USB 3.1 Gen1、USB 3.2 Gen1)なら5Gbps、USB 10Gbps(USB 3.1 Gen2、USB 3.2 Gen2)なら10Gbpsが理論上の最大転送速度となります。
一部の外付けSSDは、最大40Gbpsのデータ転送に対応したUSB4(Gen 3×2)やThunderboltといった規格を使用しています。Thunderboltのコネクタ形状は、USB-Type-C(TM)と変わりません。使用している機器がUSB4(Gen 3×2)やThunderbolt に対応している時は、外付けストレージもそれらの規格に 対応したものを選ぶのがおすすめです。また、一部の外付けHDDではeSATAやIEEE1394bといった接続規格が採用されている場合もあります。